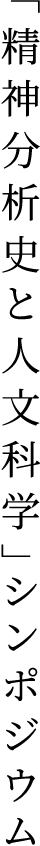CLOSS TALK BACK NUMBER
CROSS TALK
精神分析史の可能性-「見えないもの」が蒸発する時代に-
- 京都大学大学院 教育学研究科
- 西 見奈子
- 京都大学大学院 人間・環境学研究科
- 松本 卓也
- 西 見奈子
-
今日はお忙しい中、有難うございます。まずはじめに精神分析史を知ることの意義というところから考えてみたいと思っています。IPA(International Psychoanalytical Association:国際精神分析学会)の雑誌、International Journal of Psychoanalysis は年に6回の発行ですが、そこに毎号ではないのですが、年に3、4本は継続して精神分析史に関連する論文が掲載されています。
あとは、精神分析史の専門雑誌である Psychoanalysis and History ですね。こちらは1999年に創刊されて、最初の編集長は British Society に所属する精神分析家のアンドレア・サッバディーニでしたが、創刊号にはクライン派の著名な分析家であるロバート・D・ヒンシェルウッドや「フロイトの書き方」(北山修訳,1996,誠信書房)で知られるカナダの分析家で、歴史家でもあるパトリック・マホーニー、他にもフロイト・アーカイヴのエグゼクティブ・ディレクターやフロイトの改訂版スタンダートエディションの編集者など、豪華なメンバーが原稿を寄せています。
Psychoanalysis and History は元々は年2号の発行でしたが、2017年からは年3号の発行になっています。その時の編集記には「収まりきらなくなった」と書いているので、そうしたことからも精神分析史という研究分野の発展が見えてくるかと思います。
このように積み重ねられてきた精神分析史研究を精神分析を実践している臨床家が読む利点としては、まず自分たちが臨床でおこなっていることを相対化できるという点が挙げられるかと思います。またそれに加えて、そうした論文で取り上げられるトピックや分析家というのが、臨床の中のトレンドとは異なるので、単純に多くの発見がある。それだけでも十分に楽しい。それで、こうした精神分析史の研究は分析家だけがやっているかというと、決してそうではなくて、様々な分野の研究者たちが精神分析史に取り組んでいて、読者層も幅広いんですね。
じゃあ、彼らにとっての意義や魅力はどこにあるのだろうかと思うのですが、そうした辺り何かお考えがありますでしょうか。
- 松本 卓也
-
精神分析史を研究している人には、臨床家もいますが、歴史家も多いですね。精神分析史の草分け的な存在であり、早い時期にジャック・ラカンの英訳にも取り組んだジョン・フォレスターは、ミシェル・フーコーの影響を受けた歴史家でした。
フーコーは、1963年の『臨床医学の誕生』で、表面にある「見えるもの」を扱っていたかつての医学が、近代医学となる際に、表面にある「見えるもの」と深層にある「見えないもの」との関係を認識するようになったと論じています。つまり、かつての医学は身体の表面に観察できる症状を扱っていたのに対して、近代医学は病理解剖という特殊な操作によって、より深層にあるものへと向かっていったのです。
フーコーの代表作である1966年の『言葉と物』は、その図式をより一般化し、近代以降の「人間」は、深層にある「思考されざるもの」と表面との関係を扱うようになったと言っており、そのような認識のあり方のひとつの範例として精神分析を捉えていました。実際、精神分析では「無意識」という「目に見えないもの」が想定され、その「無意識」によって症状や失錯行為のような「見えるもの」が決定されていると考える。心理検査でも、たとえばロールシャッハ・テストのような「投影法」はすべてそのような想定にもとづいて組み立てられています。
ところが、現代の状況を見てみると、そのような意味での「見えないもの」が蒸発している。実際、かつての「見える」特徴をもちいて事物を分類していた博物学と違って、近代以降の生物学は、器官という「見えないもの」を認識していましたが、現代の生物学では、分子生物学やゲノム解析をみればわかるように、「見えないもの」が「見えすぎる」ほどにまで超-可視化ないし”過”視化されているわけです。それと同じことが、人間の心を扱う科学においても起こったように思えます。特に、精神分析に対する批判のほとんどは、精神分析が「見えないもの」を扱っていた点をつくものです。
- 西
-
それは、精神分析史を知ることで、近代性について捉え直すことができるということでしょうか。そのあたり個人的にとても関心があって面白く思います。と言いますのも、日本の精神分析史を考えた時に、日本の近代化と精神分析の輸入、これは明治の終わりから少しずつ始まっていくのですが、それはやはり切り離せない問題で、日本がヨーロッパをモデルに近代化しようと追い求めた理想とか、日本を近代化しようとする必死の努力とか、そういうものの中に精神分析の痕跡を認められるところがあります。
おっしゃっていただいたことは、つまり近代では「見えないもの」から「見えるもの」を考えようとしていた、でも現代では「見えないもの」が蒸発して、この蒸発というのはとても良い表現だと思いますが、その関係性が変化している、そうしたことが精神分析史からも見えてくるかもしれないということですね。
- 松本
-
はい、その意味では、精神分析に起こっていることは、他の人文科学にも同じように起こっているのかもしれない。精神分析のなかでも、「見えないもの」が蒸発している時代への応答がいくつかありますが、私には、その応答は二極化しているのではないかと思えます。一方には、神経症水準ー境界水準ー精神病水準というこれまでの病態水準の層構造に対して、「自閉症水準」のようなより深く、より「見えないもの」でありうる事柄を思考するタイプの応答です。他方には、よりプラグマティックな見地から、より浅い、というよりはむしろ「見えるもの」としての対人関係を調整したり、別の仕方で見ることを可能にするようなタイプの応答です。
- 西
-
面白いですね。おっしゃっていただいたものもそうだし、「見えないもの」を軸に考えると、今の精神分析で起きていることについて、別の分類も可能かもしれないと思いました。例えば、「見えないもの」を見えるようにする、これはもうフロイト以来の精神分析の命題ですが、むしろそうした「見えないもの」にさらに突き進んでいく方向と、「見えているもの」に焦点化して考えようとするという方向の二極化です。
前者には、やはりビオンがいて、特にいわゆるビオンの包容理論ですよね。これは、簡単に言うと、患者が感じることもできないし、意識することもできない感覚や知覚、心的な状態、そうしたものを投影同一化によるコミュニケーションを通して、治療者が言葉にしていくというものですが、こうした理論をベースに、患者もまだ言葉にできていない体験、あるいは言語が獲得される以前に体験したもの、そうしたものを精神分析の中で体験し、見えるようにしていくというのが、ひとつの大きな流れとしてあるかと思います。この流れの中には、最近、日本でもついに翻訳書が出たアンドレ・グリーン(アンドレ・グリーン著,ジャン・アブラム編,鈴木智美・石橋大樹訳「アンドレ・グリーン・レクチャー:ウィニコットと遊ぶ」2021 金剛出版)を筆頭としたフランスの精神分析の発展も加わるものだと思います。
その一方で、後者に相当するのが、見えているものに焦点を当てるアプローチです。こちらはアメリカの精神分析の独自の発展として考えても良いと思いますが、関係論の流れがあります。あとはこの流れに位置付けられるのは、メンタライゼーションでしょうか。こちらもつい先日、良い本が出ましたが(池田暁史「メンタライゼーションを学ぼう」2021,日本評論社)、どちらも、今、とても注目を集めていると思います。これらに共通するのは、無意識ではなく、意識や意識に近いものを扱うアプローチで、「見えるもの」により焦点づけた流れとして、ある意味では現代の、「見えないもの」が蒸発している時代への応答として考えられるものなのかもしれませんね。
- 松本
-
フーコーは、「見えないもの」と「見えるもの」の関係が問われる「人間」の時代はやがて過ぎ去り、「〈人間〉の終焉」がやってくるのだと予言しましたが、現代の精神分析はまさに「見えないもの」の終焉によって危機に立たされているのかもしれません。だとすれば、同様の危機は他の人文科学にもみられるかもしれません。私たちが立ち上げたこのプロジェクトは「精神分析と人文科学」と銘打っていますが、精神分析はドイツ文学、フランス文学とも深い関係にあります。今回のシンポジウムではシュルレアリスムの研究をされている中田健太郎先生をお呼びしていますが、たとえば文学研究のなかには、最近では認知科学の用語を利用して作品の読解を行うものがあります。「精神分析と文学」というテーマや「精神分析的批評」を少し齧った者としては、驚くべきことですね。ひょっとすると、分断のようなことも生じているのかもしれません。
- 西
-
確かに分断はあるかもしれませんね
- 松本
-
他方で、精神分析の側も確実に変化しており、時代に応答しているのだとも言えます。もはや精神分析の理論史の古典と言ってもよい、ジェイ・R・グリーンバーグとスティーヴン・A・ミッチェルの「精神分析理論の展開」(2001 ミネルヴァ書房)の副題が示すとおり、精神分析は「欲動から関係へ」と進んでいったわけです。つまり、フロイトの欲動論から、カール・アブラハムを経て、メラニー・クラインの対象関係論へ、というわけです。京大人環の出身者である藤井あゆみさんは「 メランコリーのゆくえ : フロイトの欲動論からクラインの対象関係論へ」(2019,水声社)でその流れを綿密に追っています。さらにミッチェルは、さらに進んで関係精神分析と呼ばれる治療の始祖にもなるわけですよね。
ラカンは、言語に注目した分析家だと言われており、それは間違いではないのですが、初期から晩年に至るまでのラカンの全体像を見た場合、彼はむしろ身体に注目した分析家だったと言ったほうがいいかもしれません。たとえば、彼の「ララング」という言葉は、子どもがはじめて言語と出会ったときに身体にトラウマのような仕方で刻み込まれる言語のことです。フェアバーンの言い方にならって、フロイトはpleasure-seekingを問題とし、フェアバーン以後の分析家はobject-seekingを問題とした、と整理されることがありますが、その意味では、ラカンは欲動論、つまりpleasure-seekingの側に立ち続けた稀有な分析家であったと言えるかもしれません。ラカンの対象関係論批判や、晩年の「症状のなかで人は享楽している」という考えは、彼がpleasure-seekingのことを考え続けた証なのかもしれないのです。
- 西
-
先ほど挙げたアンドレ・グリーンですが、彼はウィニコットやビオンを多く援用するので対象関係論の流れとしても捉えることができる人だと思うのですが、彼の考えのベースはフロイトの欲動論にあります。特に私のようなイギリスの精神分析を中心に学んできて、フランスの精神分析に疎い人間にとっては、欲動論を基礎にものを考えている人だという印象が強くあるのですが、今、お話を伺っていて、ああ、そうかと、彼は分析家になる前にラカンと出会って、学んでいた人なので、その影響が彼の欲動論をベースとした考え方に反映されているのかもしれないなと思いました。
その点から言えは、確かにフェアバーン以降、対象関係論がひとつの大きな流れとなって、欲動から関係へと視点が移るわけですが、むしろ最近の対象関係論では、そうしたフランスの精神分析の影響もあって、再び欲動に関心が向いているとも言えるのかもしれません。それはあくまでも関係論やメンタライゼーションとの対比としてそう捉えることもできるという意味ではありますが。欲動 対 関係ということですね。この辺り面白いので、さらにお話をお伺いしたいところでもあるのですが、紙面も限られているので、少しシンポジウムの話に戻りたいと思います。
今回、松本先生が提出された発表概要に「精神科医ではないフロイト」と書かれていましたよね。それを見せていただいた時、私、少し驚いたんです。いえ、そう書いていただいて全く構わなくて、私にはその切り口でフロイトを取り上げることは思いつかない発想だと思って嬉しく拝見したんですけど、日本でのフロイトの紹介では「精神科医」と書かれていることがとても多いんですね。それは日本の精神分析家の多くが精神科医であることも含め、日本では精神分析と精神医学が密接に関係してきたことと無関係ではないだろうと思います。
- 松本
-
今ウィキペディアの各国語版を見てみたのですが、ドイツ語・フランス語・英語のいずれでもフロイトは「神経科医」と書かれていますね。「精神科医」と書かれているのは日本語版だけです。もちろん、当時はその2つは今ほどくっきりと分かれていないのですが、たしかフロイトはいわゆる精神科の病院では研修を3ヶ月しただけだったと思います。もちろん、クレペリンとの対立関係など、同時代の精神医学とフロイトが関係ないわけではありません。あとは、アメリカの力動精神医学もありますね。しかし、フロイト自身への精神医学の影響は、あまり目立ちません。細部にグリージンガーやクラフト=エビングの影響が見られるくらいではないでしょうか。
- 西
-
ええ、そうですね。誰がどのように取り入れ、語ってきたかという問題がそこにはあると思います。
- 松本
-
日本の医学や心理臨床のなかにどのようにして受容されていったのか、という点も、今後の精神分析史の大きなテーマのひとつでしょうね。
- 西
-
ええ、日本という括りだけではなく、精神分析が別の文化や学術領域にどのように波及していったかを検討することは、精神分析史にとって重要なテーマだと思います。今回のシンポジウムでお話いただく予定の下司晶先生は「『精神分析的子ども』の誕生―フロイト主義と教育言説」(2006 東京大学出版会)で、学校をはじめとする教育のなかでの精神分析の影響について考えておられます。そして、もうひとりのシンポジストの遠藤不比人先生が昨年、ジョージ・マカーリの「心の革命――精神分析の創造」(2020 みすず書房)を翻訳出版されています。この本の日本での出版は嬉しかった。これまでにもフロイトの伝記というものは色々ありましたけど、その時代性から精神分析が立ち上がっていく様子を描いた傑作だと思います。
- 松本
-
アンドレアス・マイヤーという精神分析を対象とする科学史家が、精神分析における歴史記述は、これまで、アーネスト・ジョーンズの「フロイトの生涯」(竹友安彦・藤井治彦共訳,1969 紀伊國屋書店)に代表される偉人伝か、それともアイゼンクの「精神分析に別れを告げよう―フロイト帝国の衰退と没落」(宮内勝 他訳,1998,批評社)のような偶像破壊的なものか、というふうに二極化していた、と指摘しています。そして、その2つのあいだには対話もない。マカーリ先生の本は、同時代の科学のネットワークのなかから精神分析が生まれてきたことを浮き彫りにしており、「精神分析史」というディシプリンのあるべき研究方法の一つを日本に教えてくれる重要な本であるように思います。
- 西
-
ええ、ぜひそうした研究が日本でもおこなわれるようになることを願っています。今回のシンポジウムを企画した意図はまさにそこにあるのではないでしょうか。
これまで精神分析史の研究発表の場としては、日本精神医学史学会、日本病跡学会などがありましたし、他にも日本精神分析協会や日本精神分析学会などでも部分的に取り上げられてきました。おそらく文学や教育、美学など、それぞれの分野でも、研究がなされ、発表がおこなわれていたかと思います。ただ、精神分析史を中心とした集まりはなかった。
今回、このシンポジウムの名前を考えていたときに、松本先生から「精神分析史と人文科学」というご提案いただいて。実はお聞きした時には、ちょっと長すぎて説明的すぎるかなと思っていたんです。もっと違う名前、例えばブルームズベリー・グループとかイマーゴみたいな(笑)、そういう名前が良いなと思っていたんですけど、でもしばらく時間を置いて眺めているうちに良い名称だと思うようになって。この名前の通り、精神分析史を中心に据えて、人文科学の人たちが一同に集まると、これまでこぼれ落ちていたものが拾えるんじゃないか、見えていなかったものに光を当てることになるんじゃないか、そう思っています。多くの方が精神分析史に触れてくださることを何より期待しています。
CLOSS TALK BACK NUMBER
「精神分析史の多様性」
- 成蹊大学 文学部 教授
- 遠藤不比人
- 同志社大学
グローバル・コミュニケーション学部
嘱託講師 - 藤井あゆみ
- 遠藤不比人
-
私はメラニー・クラインが英国に移住して決定的な影響をロンドンの精神分析に与えるばかりか、同時代のモダニズム文学(ヴァージニア・ウルフを中心に)にも大きなインパクトがあったことを研究しているのですが、その文脈で、藤井先生のご著書(『メランコリーのゆくえ————フロイトの欲動論からクラインの対象関係論へ』水声社、2019年)が非常に重要な意味を帯びています。私は、クラインを受容したいわゆる「ブルームズベリー・グループ」と精神分析との関係に特に関心があり、アリックスとジェイムズ・ストレイチー、ウルフなどがそのメンバーです。その研究の発展として、クラインだけでなく、クラインに影響を与えたそれ以前の精神分析を勉強する必要があり、それはベルリンの精神分析協会、特にカール・アブラハムの重要性を意味します。その意味で、藤井先生のご著書は、アブラハムからクラインへの系譜を「メランコリー」という観点からじつに精密かつ広範な視点から歴史記述したお仕事で、大変に刺激を受けました。もっと言えば、フロイトからアブラハム、そしてクラインとシャーンドル・ラドーにつながるメランコリーの理論的かつ歴史的な系譜を見事に記述したお仕事で、少なくとも英語圏ではここまで徹底した研究はないはずです。
- 藤井あゆみ
-
ありがとうございます。もったいないお言葉をいただき恐縮です。拙著の書評をしていただいた遠藤先生と、私のような若輩者が対談できるなんて光栄です。私は、拙著のあとがきにも書きましたが、ただただ「メランコリー」に興味を持って精神分析理論を勉強し始めました。そしてメランコリーに関する研究を中心にたどっていったところ、アブラハムとラドーの論を見つけ、クラインに行き着いたという感じです。ですから、フロイト−アブラハム−ラドー−クラインという順に、つまりほぼクロノロジカルに彼らのメランコリー論を読み進めたため、互いの影響関係も見出しやすかったです。拙著では、メランコリー論をきっかけに精神分析における「対象」という概念が自我の性格や超自我の形成にまで関係する重要なものになっていき、超自我形成説の主軸が父子関係から母子関係へ漸進的に移行していったという点をまずは描き出しました。
- 遠藤
-
私の文脈ではメランコリーはもっぱら「母娘関係」という文脈で意味を持ちます。クラインがロンドンに来た1920年代は、母娘関係に大きなジェネレーション・ギャップがあった時代でした。たとえば、アリックス・ストレイチーの場合は、母親がラディカルなフェミニストで英国における女性参政権運動の歴史に名を残す存在なのですが、その娘の世代はどこかそのあとでノンポリ化して戦後の消費社会を文化的に享受する傾向があります。そのような娘に政治的に過激な母親がメランコリックに内面化されて強烈な超自我となって心と体の内部で暴れるというような心的光景が頻発します。ウルフの場合ですと、逆で、典型的なヴィクトリア朝的な良妻賢母型の母親が、知的な自己実現を目指す娘を内部から抑圧する超自我となるのですが、それが亡霊というような文学的イメージを得ます。ちなみにメランコリーとは対象を食べる=内面化することを意味しますが、この食べられて内面化した母=超自我は、しばしば体内の糞便というイメージとなり、それの滞留は「便秘」となって娘を苦しめたりします。アリックスの書簡などで、そういった身体症状がしばしば告白されます。ウルフは母娘関係を描いた『燈台へ』(1927年)を脱稿したあとで、自分は精神分析を自分でしたと日記に書き、またその脈絡で下水管から汚水が流れでる光景を書いたりします。一種の精神分析的な下剤のようです。
- 藤井
-
まさにその通りで、アブラハムが指摘していたことですが、メランコリー(躁うつ病)患者は下痢と便秘を繰り返す、そういうサイクルがあるんですよね。愛する対象から幻滅を味わわされると、対象への愛と憎しみのアンビヴァレンツによって、患者は内界に取り込んでいた対象(表象)を破壊して、外界へと排泄しようとします。これが下痢として現れます。そしてその対象を再び取り込み、内界で保持しようとするのですが、これが便秘という現象になるんです。患者のなかで対象と糞便が同一視されることによって、このような現象が起こってしまうわけですが、メランコリー患者の観察から、アブラハムはとくに対象の破壊と排泄が結びついていることを強調しました。その影響を受けてクラインが、糞便を母親に投げ込んで攻撃するという乳児の無意識的空想を理論化するに至ります。精神分析理論に親しんでいないとかなり突飛な話に聞こえるかもしれませんが……。
- 遠藤
-
アリックスがクラインを発見した時のことに触れると、それは1925年のベルリンの精神分析協会でした。まったく偶然にクラインの発表を聞き、非常なる感銘を受けるわけです。その際に、クライン的な超自我に感動します。これはメランコリックに内面化された母親=超自我です。この超自我は荒ぶる恐ろしいものですので、それの緩和を目的とするクラインの理論に即座に強く惹かれます。他方、それを批判するアンナ・フロイトの自我心理学的アプローチ、つまり超自我を強化する方向を、おぞましい教育者的暴力として怖気をふるいます。その背景には、強烈な教育ママであった母親がいるのでしょう。アリックスは、それ以前にウィーンでフロイトに分析を受けますがそれには不満で、その後ベルリンでアブラハムの分析を受けて豊かな経験をします。クラインと一緒にベルリンで、分析医としてアブラハムは、フロイトよりもずっといいよね、みたいに盛り上がっています。対照的に、夫のジェイムズはフロイトの分析にハマります。ちなみに、メランコリーではクラインと同じ系譜にあるラドーは、ベルリンでクラインにたいして批判的だったりします。その点についてお伺いします。
- 藤井
-
ラドーは、クラインやアリックスから見れば、かなり保守的で頭の固い人物で、クラインの早期超自我説を批判し、クラインに激しく対立した人物です。しかし、その理論を見ると、ラドーとクラインは互いに対立し合いながらも、いや、対立していたからこそ強い影響を与え合っていたと言えると思います。ラドーはアブラハムに分析を受けたのですが、その際、エディプス・コンプレクスの問題は出てこず、むしろ前エディプス期の母子関係の問題のほうが出てきたんです。ラドーには、母親にまつわる論考がいくつかあり、「メランコリーの問題」はもちろんのこと、その直前に執筆された「心配性の母」なども興味深い論考です。
- 遠藤
-
メランコリーは私の文脈では、申し上げたような歴史的文脈から、もっぱら母娘関係として問題になるのですが、もともとのフロイトの文脈ではそうではないと思います。そこでフロイトにおけるメランコリーの理論的かつ歴史的脈絡についてお尋ねをしたいと思います。もしかしたら戦争という文脈はありますか?
- 藤井
-
結論から申し上げると戦争はあまり関係ないと思います。というのも、フロイトが「喪とメランコリー」を発表したのは1917年ですが、執筆したのは1915年で、その当時、フロイトはまだ戦争をわりと楽観視していた部分があるからです。
戦争という歴史的背景よりも、精神分析の皇太子と呼ばれていた愛弟子ユングの離反の危機により、フロイトは自らのリビード論の再考を余儀なくされたので、こちらの問題のほうが大きかったと言えるのではないでしょうか。メランコリー論執筆の前年、1914年にフロイトは「ナルシシズム」の概念を精神分析理論に導入し、リビードが対象から自我へと引き戻される二次ナルシシズムという状態を考察します。そしてさらに、幼年期のナルシシズムをもとに形成される「自我理想」という概念を誕生させます。この概念は「喪とメランコリー」の論考で自我を批判的に監視し、攻撃するサディズムを備えた「批判的審級」と呼ばれるものと結びつき、1923年の著作『自我とエス』において「超自我」の概念が産み落とされるという流れになります。フロイトのメランコリー論のキーワードを考えるとき、「ナルシシズム」と「サディズム」を外すことはできませんが、メランコリーにおけるサディズムの問題をフロイトよりも重視していたのがアブラハムになります。
- 遠藤
-
フロイトのメランコリーからアブラハムへのつながりについていうと、忠実な弟子であるアブラハムがフロイトに手紙を書き、教授のメランコリー論は非常に素晴らしいのですが、これを追求すると前エディプス期の口唇性の問題になり、そこでは母子関係が前景化してきますと言ったところ、フロイトは返信で、それは私が十分にやっていないところなので期待しているよ、みたいなやりとりがあります。その意味でどこか、フロイトにとって「喪とメランコリー」という論文は、痛し痒しみたいなところがあったのかもしれません。つまり、この理論を契機にして、アブラハムを経由しながら、クラインという鬼っ子が誕生してしまったと言えます。
- 藤井
-
そうですね。アブラハムが口唇サディズムを強調したことによってクラインの「破壊的乳児」が生み出されたわけですが、クラインを異端者と捉えるか、はたまた革命児と捉えるかは学派によって分かれるところです。拙著でも触れたことですが、ウィーンで現在活動中の分析家のフリューはアブラハムのせいでクラインのような異端が生まれたと批判しますし、ベルリンで活動するマイなんかはアブラハムの革命的理論のおかげでクラインが誕生したという見解を示しています。
ベルリンにはアブラハムとアイティンゴンが1920年に創設した世界初の精神分析インスティテュートがあり、そこではとても自由に議論がなされていたために、クラインもラドーも独自の理論を立てることができたんだと思います。当時のベルリンにはホーナイもアレクサンダーもいました。彼らはアメリカに渡り、いわゆる正統派とは一線を画するようになります。フロイト理論をドグマ化するのではなく、刷新していこうという気風がベルリンで育っていたと言えるのではないでしょうか。しかし他方で、ハルトマンのような正統派に数え入れられるような分析家たちもラドーの教育分析を受けてアメリカで活躍するようになります。ラドー自身はのちに異端として扱われるようになるのですが……。正統であれ、異端であれ、後世に名を残すような分析家たちが多く輩出したベルリン精神分析インスティテュートは非常に興味深い機関だと思います。また、当時のベルリンのインスティテュートにはすでに児童分析を行うグループも存在していて、そこでクラインが頭角を現すようになるんですね。彼女と対立していたラドーは分析家養成課程を作成した一人でして、分析実践も教育課程もベルリンでは一気に発展していきます。アイティンゴンのおかげで教育分析と統制分析のシステムも出来上がりました。
- 遠藤
-
おっしゃるように、ベルリンでは、ウィーンとは違って、唯一無二の権威に転移することを避けて、陽性であっても陰性であっても、教育分析において転移を「散らす」というか、一人の分析家に集中させずに、組織的かつシステマティックに分析家を教育しようとしました。その辺は私が訳したジョージ・マカーリの『心の革命』にもある程度記述されています。マカーリのベルリンに関する歴史記述では、20年代にその精神分析は花開いたが、30年代になるとナチスの影響でユダヤ系の分析家がアレクサンダーを中心に米国に逃げるという構図になっていますが、この辺もう少し詳しい話ですとどのようになりますか。
- 藤井
-
じつはベルリンの花形分析家たちは、ナチスが政権を掌握する前にすでにアメリカに招聘されています。ラドーは1931年にニューヨークへ招聘され、ベルリンの教育モデルをニューヨークのインスティテュートにいち早く導入していますし、ラドーとともにベルリンの養成課程のカリキュラムを作成したアレクサンダーはラドーよりもさらに早くシカゴ大学の精神科に招聘されています。そして彼はシカゴにホーナイを1932年に招聘しているんです。ですので、ナチスの影響がまだそれほどない、かなり早い段階でベルリンの著名な分析家たちは渡米しています。
- 遠藤
-
私は単純にナチスから逃れるためにベルリンの優秀な分析医が米国に亡命したと考えていたのですが、お話を伺うと、精神分析を医学に統合しようとする米国では、最先端のベルリンで活躍する優秀な医者の分析家の需要があったと理解することができますか。
- 藤井
-
そうですね。渡米した分析家の多くはアメリカの大学の医学部に精神分析を根付かせるのに一役買いました。とくにラドーは精神分析を医学の一分野にするのが夢でしたから。フロイトはそれには反対していたんですが……。
- 遠藤
-
ベルリンでも医学の学位のあった分析家と素人分析家(lay analyst)という問題があったかと思うのですが、ベルリンで教育分析を組織化することに多大な貢献をしたアイティゴンはその意味でどのような位置付けになりますか。
- 藤井
-
アイティンゴンは、医学の博士号を取得しながらも医師国家試験は受けずに医師見習いとして働いていた趣味人でして、アブラハムが「アイティンゴンは分析を手伝ってくれない」とフロイトに嘆いていたことからもうかがえますが、実践からは逃げ続けた人という印象があります。その代わり、彼は患者をどの分析家に回すか、などといった運営面の仕事をしたり、統制分析(スーパーヴィジョン)を導入し、教育委員会を組織したりしています。さらに彼はベルリンの教育委員会を国際化し、その議長を務めるまでになります。この教育委員会のメンバーにはラドー、ホーナイといったベルリンの中心人物たちが揃えられていました。メンバーには医学を修めた分析医も、素人分析家(非医師分析家)もいて、アイティンゴンは分析家の医師免許の有無の問題に悩まされるわけですが、玉虫色の解決策を提示します。それは、分析家候補生は医学教育を受けているほうが望ましいが、非医師のための門戸も開かれたままにするという折衷案でした。しかしニューヨーク支部はこれに猛反発し、ニューヨークでは非医師分析家を容認しないという決定が下されます。
- 遠藤
-
その後ウィーンのフロイトの高弟たちがニューヨークに亡命してくると、そこにすでにいて精神分析の医学=脳科学化を推進していたラドーを激しく批判するという展開になりますね。フロイト自身は、精神分析を医学部を超えるものと考えていましたから。その点からベルリンを考えると、アブラハムの人格とアイティンゴンの折衷主義などがあり、一方でアレクサンダーやホーナイのような医学者として傑出した分析家がいて、他方クラインのように医学的知識が皆無の素人分析医をアブラハムが認めて場所を得るというような、開かれて自由な空気があったようですね。その一方で、ベルリンは二重の意味で、フロイトから離反する可能性も宿していたようで、一つは精神分析の医学化路線であり、もう一つは素人分析家による母子関係を中心とした子供の分析がそれであって、後者を代表するクラインがロンドンに行くと、ロンドンvs.ウィーンという構図が出てきます。そしてロンドンには、ジョウン・リヴィエールという強力な存在がいたわけです。クラインをロンドンに連れてきたのはアリックス・ストレイチーですが、その後理論的な闘争になるとアリックスもジェイムズもブルームズベリー・グループ的な優雅な高等遊民としてそこから距離を置くようになり、その代わりにウィーンのアンナ・フロイトからクライン理論を断固として擁護したのがリヴィエールでした。リヴィエールは極めて優秀な翻訳者としてフロイトから認められていました。それと同時に、フロイトにも分析を受けていました。フロイトは『自我とエス』の脚注でこの分析に暗黙のうちに触れて、女性患者の分析において父性の陽性転移が有効であるみたいなことを言うのですが、リヴィエールはそれに反論しています。女性患者の男性分析家にたいする陽性転移は、ある種の仮面であって、それによって遮断されるので、男性分析家は前エディプス期のメランコリックに内面化された母娘関係は分析できないという論文を書いています。しかし話は複雑で、このメランコリックな強度はほとんど分析不能な狂気でもあり、その意味で男性分析家への陽性転移は仮面であるのと同時に、ある種の防衛でもあるという議論になっています。少なくとも戦間期の精神分析においては、メランコリックな母子関係は、クライン派においても、分析困難な強度を帯びていたようです。
- 藤井
-
そうですね。「ポスト・クライン派」になるとさらに発展した理論が出てきて、分析困難なところにも踏み込んで行っているように見えます。ただ、私はまだポスト・クライン派についてあまり勉強できておりませんので、ほとんど何も申し上げられませんが……。
- 遠藤
-
いまおっしゃった「ポスト・クライン派」の理論的可能性については、この研究グループの西見奈子先生と鈴木菜実子先生たちによる共著『精神分析にとって女とは何か』(福村出版、2020年)という大変な名著があり、日本の精神分析という文脈も踏まえながら、優れた歴史的かつ理論的記述をしています。
- 藤井
-
そうですね。西先生と鈴木先生にまたじっくりとお話を伺いたいところです。前エディプス期の母子関係という点では、じつはすでにラドーがけっこう論じていて、乳児の空腹の不快感が攻撃性につながるという見解をいち早く示しています。彼は、乳児の「怒り−空腹−授乳」という連鎖が幼児の「罪−償い−赦し」の連鎖の原型だと指摘しているんですね。もう少し詳しくお話しすると、母親不在時の空腹状況と「寄るべなさ」によって乳児に生じた怒りから、その後のあらゆる攻撃的拒絶反応の形態、例えば、食い尽くす、噛みつく、殴る、壊滅させるといった形態が生じ、乳児が大きくなってから、つまり事後的に罪責感が生じて償いを行うという流れをラドーは描き出しました。
- 遠藤
-
藤井先生の著作の卓越した要素の一つが、ラドーの理論を詳しく記述した点で、私はクラインを読んでラドーは読んでいないので、その辺大変に勉強になりました。
- 藤井
-
お褒めいただいて光栄です。ラドーはクラインに先んじて「良い母親」と「悪い母親」の分裂した二様の表象が子どもに存在し、メランコリー患者ではこの「二様の体内化過程」が問題になると、1927年(英訳1928年)に発表しています。この論文をクラインは引用していますし、ラドーから影響を受けていることは明らかです。
- 遠藤
-
普通、「良い母親」と「悪い母親」というと、ほぼ自動的にクラインという話になるわけですが、じつはそれ以前にラドーがそれについて論文を書いているという事実はそれほど共有されていないのではないでしょうか。いずれにしても、ラドー、アブラハム、クラインとの相互関係は、ベルリンの精神分析の理論的な豊かさの証左になりますね。
- 藤井
-
その通りです。ラドーとクラインは互いに批判し合いながら影響を与え合っていたと言えると思います。ラドーとクラインが互いに批判し合ったのは、とりわけ罪責感についての問題です。ラドーは、乳児は母親への自らの攻撃性に対して、罪責感を潜伏期になってから事後的に抱くという見解を示したのですが、この事後性についてクラインは批判し、乳児の時点ですでに罪責感は生じていると反論するんですね。でもラドーは事後的罪責感の議論を覆すことはなく、クラインと対立し続けたわけです。
- 遠藤
-
ラドーのクライン批判は興味深く、それはたとえば英国の分析家かつ理論家でもあるジュリエット・ミッチェルにも共通していて、クライン的な前エディプス期の外傷性(母による去勢など)は、その後のエディプス的な去勢の事後的な効果として理解するべきだと論じています。
- 藤井
-
ジュリエット・ミッチェルについては不勉強で何も申し上げられることはないのですが、ラドーとクラインが批判し合いながら強い影響関係を結んでいたことが、ジュリエット・ミッチェルのような分析家たちのその後の理論と実践の発展につながっていったのではないでしょうか。ベルリンではいろんな相互作用・相乗効果が生まれていたと言えると思います。アブラハムはフロイトへの手紙で、自分が論じた原気分変調(原メランコリー:親に対する幻滅から生じる幼児の最初の抑うつ状態)について、クラインが児童分析において実証してくれたと語っていますし、逆にクラインの児童分析がアブラハムの理論に影響を与えていたということもあると思います。本当に興味深い相互作用ですよね。
- 遠藤
-
藤井先生のご著書とお話を伺うと、あらためてベルリンの重要性が「メランコリー」という視点から見えてきました。ウイーンを源流としながらも、その流れがベルリンを経由して格段に豊かなものになりながら、そこでの相互作用の結果として分岐し、ロンドンとニューヨークへ流れて行った歴史的かつ理論的な意義が再認識できました。
- 藤井
-
ベルリンで花開いた多くの理論は、残念ながらあまり英訳がないですよね。アブラハムに関して言えば、英訳で読めるのはおそらくSelected Papersだけですから、重要な論文も漏れてしまっています。日本語でもほとんど訳されていませんし……。ですので、アブラハムの精神分析関係の全論文とフロイトとの往復書簡集を私が訳して出版したいと考えているのですが、日々の雑務に追われ、翻訳作業は遅々として進んでおりません。でもいつか必ず出版し、クラインの前史としても重要なアブラハムの精神分析に関する仕事の全体像をお見せできたらと思っております。
- 遠藤
-
私の不勉強もありますが、イギリスの精神分析に特化するとクライン以前の前史が見えにくいということがあり、おっしゃったようにアブラハムの仕事が英訳ではSelected Papersになっているという限界があります。一方で、先ほどのポスト・クラインの話になると、『精神分析にとって女とは何か』は、日本の精神分析に介入しています。男中心の日本の精神分析において、どうしても女=母という図式が強く、そこに娘、あるいは母娘という問題が不可視化されたという歴史的事情があるようですが、そこに英語圏のフェミニズム理論を通過したポスト・クライン的精神分析が大きな意義を発揮するという臨床的かつ理論的可能性を洞察した研究になっています。
- 藤井
-
日本の精神分析家の方々のなかにはタヴィストックでトレーニングを積まれた人が比較的多いと思いますので、ポスト・クラインと日本の精神分析は深いつながりがありますよね。今回はアンナ・フロイトにほとんど触れることができず、その点に関してはまた機会を改めて遠藤先生にお聞きしたいと思います。フロイトから離反する可能性のあったアブラハムの母子関係論をクラインが引き継いで、アンナ・フロイトと対立することになるわけですが、フロイトとアブラハムの水面下の対立が、ロンドンでアンナ・フロイトとクラインの対立として顕れ、代理戦争の様相を呈しますよね。この問題については、先ほども申し上げましたが、また機を改めてお話しできれば幸いです。遠藤先生、本日はありがとうございました。先生のお話を伺い、大変勉強になりましたし、とてもよい刺激を受けることができました。このような機会をくださった西先生と松本先生にも御礼申し上げます。